植物ホルモン「ストリゴラクトン」が機能する仕組み −化学シグナル受容後のメカニズムの一端を解明−
- 発表者
-
Zhou Feng(南京農業大学江蘇植物遺伝子工学研究センター 研究員)
上野 琴巳(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 特任研究員;当時)
伊藤 晋作(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 特任助教;当時)
浅見 忠男(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 教授)
Wan Jianmin(南京農業大学江蘇植物遺伝子工学研究センター 教授)
発表のポイント
- ◆どのような成果を出したのか
- 植物の枝分かれを抑える働きを持つ植物ホルモン(注1)「ストリゴラクトン」の受容後のシグナル伝達を明らかにしました。
- ◆新規性(何が新しいのか)
- イネ枝分かれ過剰変異体の解析より、ストリゴラクトンのシグナル伝達の新奇抑制因子D53を同定し、ストリゴラクトンを認識したD14と結合すること、結合したD53がタンパク質分解に関わるSCFD3複合体によって分解されることを明らかにしました。
- ◆社会的意義/将来の展望
- 今回の発見は、イネ等の作物の枝分かれを制御することによる収穫量やバイオマスを増加させることに加え、アフリカをはじめとして甚大な農作物被害をもたらす根寄生雑草の防除に向けた新技術開発に役立つことが期待されます。
発表概要
ストリゴラクトンは2008年に植物ホルモンとして認識された生理活性物質であり、側芽の生長を抑えることで枝分かれを抑制することに加え、土壌中の有用な菌との相互作用や、様々な作物の根に寄生する雑草の種子発芽に関わることが知られています。これまでに、ストリゴラクトンはDWARF14(D14)というタンパク質によって受容されることが明らかとなっていましたが、その後のシグナル伝達機構は解明されていませんでした。
南京農業大学江蘇植物遺伝子工学研究センターのWan Jianmin教授らの研究グループと東京大学大学院農学生命科学研究科の浅見忠男教授の研究グループ等による共同チームは、枝分かれ過剰変異体の解析により、ストリゴラクトンシグナル伝達の新奇抑制因子としてD53を同定しました。またD53はストリゴラクトンを受容したD14と相互作用し、SCFD3複合体によってプロテアソームタンパク質分解系(注2)で分解されることによって、ストリゴラクトンによる枝分かれ制御機構が発現することを明らかにしました。
本研究の成果は、新たな植物ホルモンであるストリゴラクトンのシグナル伝達機構の分子メカニズムの一端を明らかにしただけでなく、作物の枝分かれを制御し、収量やバイオマスを増加させることによる農業生産の向上や低炭素社会の実現のため、また世界の多くの地域で甚大な被害を与えている寄生雑草からの防除のための新しい技術開発に大きく役立つものと期待されます。
本研究の内容は英国化学誌「Nature」オンライン版12月11日に掲載されました。
発表内容
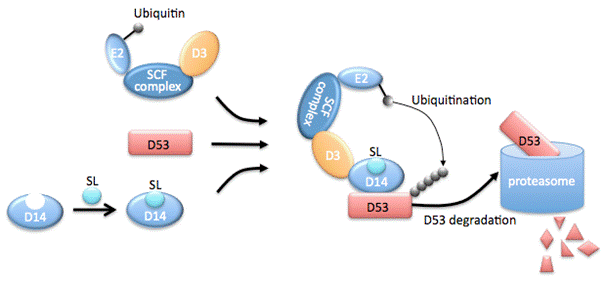
ストリゴラクトン受容体D14とD3複合体はストリゴラクトンシグナル抑制因子D53と結合して分解を誘導することで、ストリゴラクトン情報を伝達する。 (拡大画像↗)
作物の枝分かれはその植物の形や作物収量を決定する主要な要因であり、植物ホルモンや環境要因等の様々なものによって影響を受けています。最近発見された植物ホルモン「ストリゴラクトン」は、分化した側芽の休眠状態を保ち、枝分かれを抑制する働きがあり、このホルモンを作ることができない変異体は枝分かれが旺盛になります。また、ストリゴラクトンは、ストライガといった、作物の根に寄生する雑草の発芽も促します。ストライガは寄生した作物の栄養を吸い取り作物を枯らしてしまうため、農業上非常に有害な雑草として知られており、特にアフリカ地域では70億ドルもの被害がでていると言われていますが、その防除法は未だ確立されていません。
ストリゴラクトンは2008年に植物ホルモンとして知られるようになった物質であり、植物体内での生合成経路やシグナル伝達経路、植物における働き等が現在世界中で研究されていますが、まだまだ未解明の部分が多く残されています。特にストリゴラクトンの受容機構に関しては最近D14というタンパク質がストリゴラクトンを認識するということ、D3というタンパク質がプロテアソームタンパク質分解系を通して何らかのタンパク質を分解することがストリゴラクトンのシグナル伝達に必要であるということが示唆されてきました。しかし、D14によるストリゴラクトン受容後にどのようにシグナル伝達が起こっているのか?D3タンパク質がどのタンパク質をどのように認識して分解しているのか?はこれまで不明でした。
今回、南京農業大学江蘇植物遺伝子工学研究センターのWan Jianmin教授らの研究グループと東京大学大学院農学生命科学研究科の浅見忠男教授の研究グループ等による共同チームはストリゴラクトン受容後のシグナル伝達にD53というタンパク質が抑制因子として機能し、D3タンパク質により分解されることでシグナル伝達が進むというユニークな仕組みを明らかにしました。
これまでにd53変異体が「多分げつ矮性形質」という、ストリゴラクトン欠損変異体に特徴的な形態を示すということが分かっていました。そこで研究チームは、d53変異体の形態を詳細に解析したところ、d53変異体では枝分かれが増大しており、外部からストリゴラクトンを加えても枝分かれが通常に戻らないこと、植物体内のストリゴラクトン量が過剰に蓄積していることから、ストリゴラクトンのシグナル伝達に変異が起きている可能性を見いだしました。またd53変異体ではClp ATPaseファミリーと相同性の高いタンパク質(D53タンパク質)の働きが変化しており、D53がストリゴラクトン存在時のみD14と結合し、核に局在することを明らかにしました。
さらにD53にGFPと呼ばれる蛍光タンパク質やルシフェラーゼと呼ばれる発光酵素を結合させ、イネに発現させたところ、ストリゴラクトン存在下でのみ、D53−GFPの蛍光やD53−ルシフェラーゼの発光が抑制され、変異型d53タンパク質やプロテアソームタンパク質分解系の阻害剤であるMG132を処理した場合はこれらの抑制が観察されなかったことから、ストリゴラクトン存在下でD53タンパク質がプロテアソーム分解系を通して分解されており、D53の分解がストリゴラクトンのシグナル伝達に重要であることが示されました。
以上の結果により、ストリゴラクトンはD14を認識した後、ストリゴラクトンシグナルの抑制因子であるD53と結合し、D3を含むプロテアソーム分解系によってD53が分解されることによりシグナル伝達がおこなわれるという受容・シグナル伝達モデルを提唱しました。
本研究は、収量やバイオマスを増加させることによる農業生産の向上や低炭素社会の実現のための新技術開発に有用な基礎研究基盤となるものです。また、世界の多くの地域で甚大な被害を与えている寄生雑草の新しい防除法の開発にも大きく役立つものと期待されます。
本研究は生物系特定産業技術センターイノベーション創出基礎的研究推進事業「有用物質・遺伝子・形質の探索と応用を目指した植物ケミカルバイオロジー研究」の支援を受けて行われました。
発表雑誌
- 雑誌名
- 「Nature」online 11 December 2013
- 論文タイトル
- D14-SCFD3-dependent degradation of D53 regulates strigolactone signalling
- 著者
- Feng Zhou, Qibing Lin, Lihong Zhu, Yulong Ren, Kunneng Zhou, Nitzan Shabek, Fuqing Wu, Haibin Mao, Wei Dong, Lu Gan, Weiwei Ma, He Gao, Jun Chen, Chao Yang, Dan Wang, Junjie Tan, Xin Zhang, Xiuping Guo, Jiulin Wang, Ling Jiang, Xi Liu, Weiqi Chen, Jinfang Chu, Cunyu Yan, Kotomi Ueno, Shinsaku Ito, Tadao Asami, Zhijun Cheng, Jie Wang, Cailin Lei, Huqu Zhai, Chuanyin Wu, Haiyang Wang, Ning Zheng and Jiamin Wan
- DOI番号
- 10.1038/nature12878
- アブストラクト
- http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/pdf/nature12878.pdf
問い合わせ先
東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物制御化学研究室
教授 浅見 忠男
Tel: 03-5841-5157
Fax: 03-5841-8025
研究室URL: http://pgr.ch.a.u-tokyo.ac.jp
用語解説
- (注1) 植物ホルモン
- 植物により生産され、低濃度で植物の生長・分化などの生理過程を調節する物質。
- (注2) プロテアソームタンパク質分解系
- ユビキチンで修飾されたタンパク質を選択的に破壊するタンパク質分解系。ユビキチン化活性化酵素(E1)・転移/結合酵素(E2)・リガーゼ(E3)からなるSCF複合体で構成される。